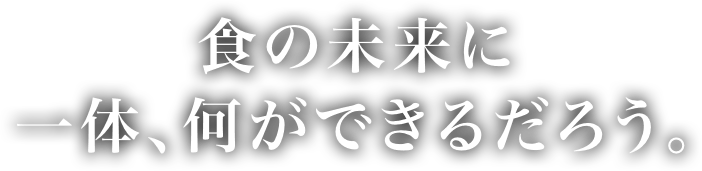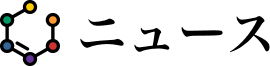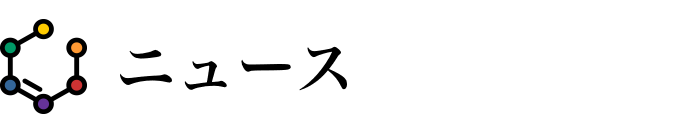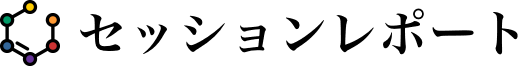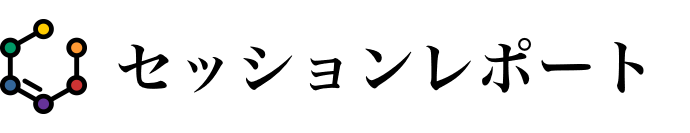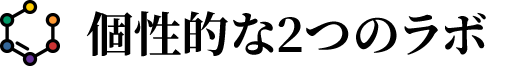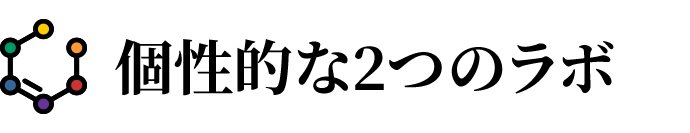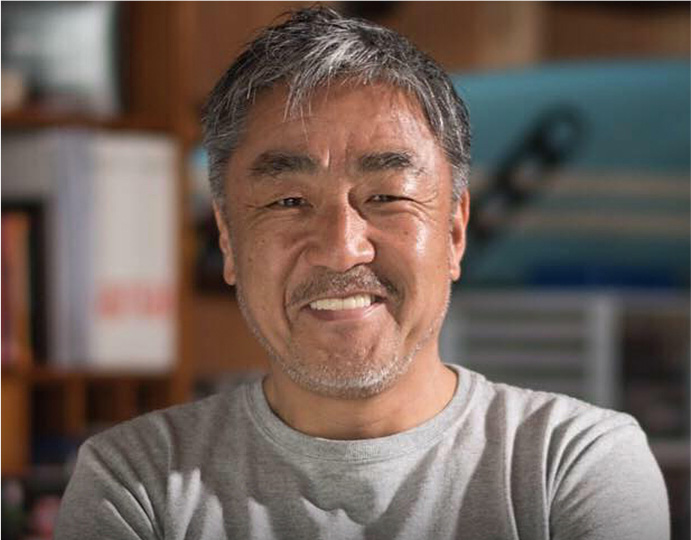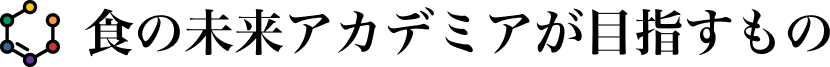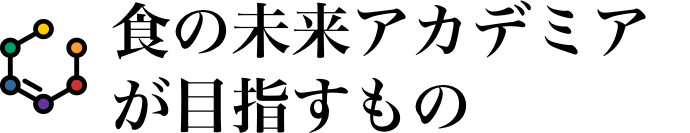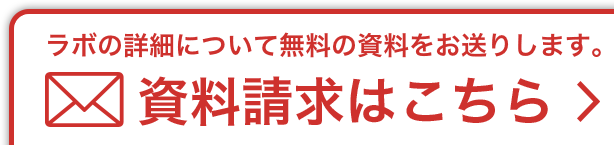「食」の世界は、広くて、深い。
飲食店、家庭の食卓、1次産業、ものづくり、健康、テクノロジー、地域コミュニティ、
ブランディング、おもてなし、街づくり、食育、情報コミュニケーション、働き方。
「食」のまわりには、ありとあらゆるテーマが複雑に絡み合っています。
本来は「生命維持のために栄養を摂取する」という極めてシンプルな行為であるはずなのに、
気づけば「食」には、社会や未来をより良いものにしていくという
極めて大切なミッションが与えられたようです。
「食の未来アカデミア」は、食に関するエッジのきいたテーマを掲げて、
それについて様々な角度から知り、議論をしていく新しい学びの場です。
一人ひとりの想いやアイディアから食の未来が生み出される、そんな拠点になることを目指しています。
飲食店、家庭の食卓、1次産業、ものづくり、健康、テクノロジー、地域コミュニティ、
ブランディング、おもてなし、街づくり、食育、情報コミュニケーション、働き方。
「食」のまわりには、ありとあらゆるテーマが複雑に絡み合っています。
本来は「生命維持のために栄養を摂取する」という極めてシンプルな行為であるはずなのに、
気づけば「食」には、社会や未来をより良いものにしていくという
極めて大切なミッションが与えられたようです。
「食の未来アカデミア」は、食に関するエッジのきいたテーマを掲げて、
それについて様々な角度から知り、議論をしていく新しい学びの場です。
一人ひとりの想いやアイディアから食の未来が生み出される、そんな拠点になることを目指しています。
「食の世界で新しいプロジェクトを起こしたい」「食を通じて世の中を良くしたい」。
そうした思いやアイディアの欠片を抱えている人はたくさんいますが、
いざそれを実現していくためには、一人ではとても力が足りません。
ひょっとすると家族やこれまでの友人知人のネットワークだけでも、十分ではないかもしれません。
そこに必要なのは、視野を広げてくれたり、アイディアを膨らませたり、
時には本気で批判をしてくれる他者の存在です。
私たちはそんな「場」をつくりたいと思って、「食の未来アカデミア」を立ち上げました。
面白いメンバーが集い、そこに面白いゲストを招き、面白い議論が巻き起こる。
そして、面白いプロジェクトが動き出す。
これからの時代に「学びを核としたコミュニティ」には大きな可能性があると思っています。
そうした思いやアイディアの欠片を抱えている人はたくさんいますが、
いざそれを実現していくためには、一人ではとても力が足りません。
ひょっとすると家族やこれまでの友人知人のネットワークだけでも、十分ではないかもしれません。
そこに必要なのは、視野を広げてくれたり、アイディアを膨らませたり、
時には本気で批判をしてくれる他者の存在です。
私たちはそんな「場」をつくりたいと思って、「食の未来アカデミア」を立ち上げました。
面白いメンバーが集い、そこに面白いゲストを招き、面白い議論が巻き起こる。
そして、面白いプロジェクトが動き出す。
これからの時代に「学びを核としたコミュニティ」には大きな可能性があると思っています。

学長:子安大輔