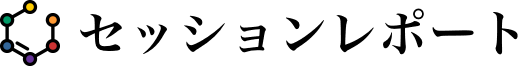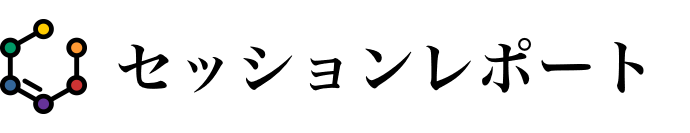【ゼロイチラボ セッションレポート】
「ものすごく面白そうな食のイベントがあるんだけど」。知人にそう言われたら、「行く!」と即答するような人であっても、それが1回15万円と聞けば躊躇してしまうケースがほとんどではないだろうか。大類知樹さんが代表を務める株式会社ONESTORYが仕掛ける「DINING OUT」は金銭的にはまさにそれくらい高価なのだが、なんとそのチケットは毎回瞬く間に完売してしまうという(ちなみに現地集合・現地解散なので、移動にかかる航空券などは別途となっている)。
DINING OUTは、「日本の地域で数日だけオープンするプレミアムな野外レストラン」である。2012年に新潟県・佐渡島で第1回が開かれたのを皮切りに、静岡県・日本平、北海道・ニセコ、愛媛県・内子など、日本各地を舞台にしてこれまでに12回が実施されている。ミシュランガイドで星を獲得しているようなレストランのトップシェフたちが、特定の地域に深く入り込み、その技術とクリエイティビティを生かして、「土地の魅力」を掘り起こしている。
各地で開かれる「レストラン」は基本的にはたった2日間だけである。しかし、その2日間のために、DINING OUTのチームは半年以上前からその地域に入り込み、リサーチを始める。どこに魅力的な生産者がいるのか、その土地の伝統的な食材や調理法は何か、歴史的・文化的にどのような背景があるのか、レストランの舞台となる象徴的な場所は果たしてどこなのか。こうしたことを徹底的に調べ上げ、シェフと随時情報を共有しながら、企画を練っていく。シェフ自身も忙しいスケジュールの合間を縫って、頻繁にその地域に足を運び、自らの五感で土地への理解を深めていく。
最終的なアウトプットは華やかで創造的なものだが、そこに至る過程は非常に泥臭い。東京の人間が突然やってきたところで、地元の方たちはそう簡単に受け入れるわけではない。スタッフたちは、生産者たちと夜な夜な酒を酌み交わして語り合い、また地元の有力者や情報が集まっているスナックに足繁く通うことで、徐々に距離を縮めていくのだ。こうして集めた膨大な情報やネットワークをもとに、企画を研ぎ澄ましていく。
研ぎ澄ますと言えば、このDINING OUTのターゲット設定も実に練られている。4000人を対象にしたリサーチによって、人々の価値観をあぶり出している。その中で「食」や「地域」、そして「文化」への関心が極めて高い人たちを「カルチュラル・クリエイティブ・クラス」と定義し、彼らだけをターゲットにしている。この人たちは人口推計で全体の約1%しか存在しない。DINING OUTはこのたった1%に向けて、すべてを設計しているのだ。
大類さんは言う。DINING OUTのプラニングのポイントは「狭く、深く、濃く」であると。それぞれの地域をどれだけ深く理解し、そして極めて狭くターゲティングされた顧客に対して、いかに濃密に表現することができるか、それにかかっているということだ。舞台となる自治体、そして企画に協賛している企業からすれば、言いたいことは山ほどあるはずだ。しかし、それを必要以上に意識しては、「広く、浅く、薄く」になってしまいかねない。この点をぶらさずに忠実に守っていることが、DINING OUTの実績と評判に直結しているに違いない。
それにしてもなぜ大類さんはこんな手間のかかる壮大なプロジェクトを始めたのだろう。「地方には可能性がたくさんあるはずなんですけれど、あまりにもその発信の仕方がダサいと常々感じていました。そこをきちんと表現してあげれば、もっと価値を発揮できるはずなんです」。さらに続ける。「地方における食の発信というと、『B級グルメ』ばかりでした。もちろんそれが決して悪いというわけではありません。でも、その土地に住んでいる人が誇りを感じるのは決してB級なものではないはずです。むしろ『A級』の価値を発信することこそが、地域にとってはプラスになるはずなんです」。
DINING OUTがこうして各地の「A級」の価値を発信し続けることで、全国の自治体から続々とオファーが舞い込んでいると言う。ONESTORY社としては、今後も新たな地域の魅力を掘り起こして発信するとともに、これまで関わった地域についても継続的に活性化する取り組みを実施しているとのこと。歴史も文化も異なる日本の各地が、こうしてA級の魅力を発信していく未来を、引き続き同社には支援してもらいたい。
【ゼロイチラボ セッションレポート】